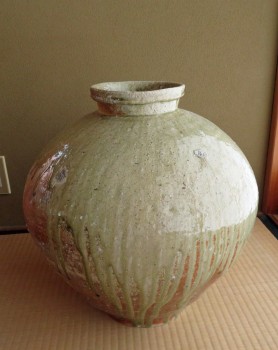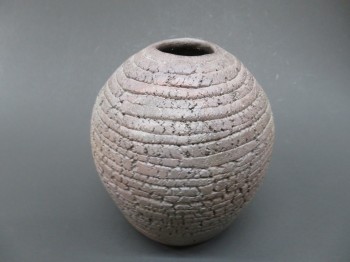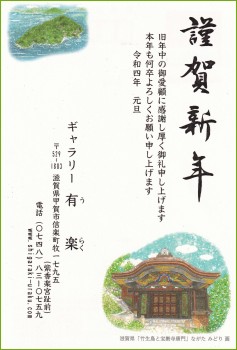澤 克典(さわ かつのり)氏の作品を紹介します。
信楽では今桜が見頃になり華やかな桜色の空気に包まれています。
その脇でゆきやなぎ、さんしゅう、きぶし、みずき、くろもじが
小さい可愛い花を精いっぱい咲かせ春らしい景色を作っています。
遠出をして花見をすることもできず、
もっぱら散歩を兼ねて一人花見を楽しんでいます。
ゆっくりと美しい桜を愛でながらそよ風に吹かれ
暖かな日差しに包まれているだけで
ただただ幸せで平和なひと時。
良い季節になりましたが喜べないことの多い日々の情報。
やわらかい芽を吹き美しい花を咲かせる草木に励まされながら
何か少しでも新しいことにチャレンジしていきたいと。
くろもじの花の香りがやさしく匂っています。
(ゆきやなぎ)